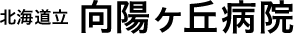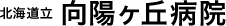No.5 発達症
発達症については、診断基準が徐々に変更されてきており、有病率も調査では増えてきていますが、実際に増えているのか、診断する側の問題なのか分かっていません。自閉スペクトラム症の有病率は子どもでも大人でも1%、注意欠如・多動症の有病率は子どもで5%、成人で25%と言われています。
自閉スペクトラム症は、もともとアスペルガー症候群や、自閉症、高機能自閉症などと言われていた発達症を知能や言語の障害の有無に関わらずひとくくりにしてとらえたものです。社会的な相互交渉の質的な障害、コミュニケーション機能の質的な障害、イマジネーションの障害が代表的な特徴とされます。これらの障害により、人の輪に入るのが苦手で、年齢相応の交友関係が作れなかったり、他人の感情や、自分の感情をうまく把握できなかったり、場の雰囲気を読めず場にそぐわない言動、行動をしたり、同じものや動作、仕草にこだわり、些細な変化についていけなかったりなど、日常生活上の困難が生じてきます。症状は発達早期(就学前)から存在していますが、軽症の場合には、幼少時には大きな問題が生じず、高校や大学に進学したり、就労して、本人に求められる能力が複雑化したり、親元を離れたりして周囲のサポートが減少した場合に問題が表面化することもあります。自閉スペクトラム症に対する根本的な治療は今のところなく、大人になっても本人の特性、成長に合わせたサポートを行っていくことが必要となります。また、社会関係や人間関係の問題からストレスを抱えやすく、うつ病などの精神疾患になる場合も多いため、併存する病気への対応も必要になってきます。
注意欠如・多動症については、不注意あるいは多動性注意欠如・多動症については、不注意あるいは多動性12歳(以前の基準では7歳)までに存在し、症状が2つ以上の状況(例えば、家庭、学校、職場、友人や親戚といるとき、その他の活動中)で存在することが診断基準となっています。多動性衝動性については、幼少期に目立ちますが成長に従って軽減していくことが多く、不注意症状は成長しても残存することが多いです。最近、幼少期には問題なく成人になってから発症する注意欠如・多動症が存在するのではないか?との仮説も発表されていますが、現状では否定的な立場の研究者が多いです。注意欠如・多動症については、有効な薬剤が開発されてきています。
いずれの発達症も、少なくとも小学生の時には症状が出現していることが診断基準となっています。成育発達途中に症状が問題化するのが発達症であり、大人になってから発達症と同様な症状が出現したとしても、それは発達症とは考えないのが原則です。その点を見落とされて、ネット上の診断ツールなどで判断して精神科や心療内科に相談に来られる方は、実際には発達症ではなく、他の病気であることがほとんどです。